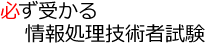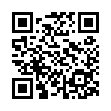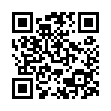- トップページ
- 応用情報技術者
- 平成30年度春季問題
- 平成30年度春季解答・解説
平成30年度春季解答
問題11
メモリインタリーブの説明として、適切なものはどれか。
| ア | 主記憶と外部記憶を一元的にアドレス付けし、主記憶の物理容量を超えるメモリ空間を提供する。 |
| イ | 主記憶と磁気ディスク装置との間にバッファメモリを置いて、双方のアクセス速度の差を補う。 |
| ウ | 主記憶と入出力装置との間でCPUとは独立にデータ転送を行う。 |
| エ | 主記憶を複数のブロックに分けて、CPUからの並列的にアクセス要求を並列的に処理できるようにする。 |
解答:エ
<解説>
メモリインターリーブとは、メモリのデータ転送を高速化する技術の一つ。複数のメモリバンクに同時並行で読み書きを行うことにより高速化を行う手法である。
| ア | × | 主記憶と外部記憶を一元的にアドレス付けし、主記憶の物理容量を超えるメモリ空間を提供する。 →仮想記憶の説明である。 |
| イ | × | 主記憶と磁気ディスク装置との間にバッファメモリを置いて、双方のアクセス速度の差を補う。 →キャッシュメモリの説明である。 |
| ウ | × | 主記憶と入出力装置との間でCPUとは独立にデータ転送を行う。 →ダイレクトメモリアクセス(DMA)の説明である。 |
| エ | 〇 | 主記憶を複数のブロックに分けて、CPUからの並列的にアクセス要求を並列的に処理できるようにする。 →メモリインターリーブの説明である。 |
問題12
USB3.0の特徴として、適切なものはどれか。
| ア | USB2 . 0は半二重通信であるが、USB3 . 0は全二重通信である。 |
| イ | Wireless USBに対応している。 |
| ウ | 最大供給電流は、USB2 . 0と同じ500ミリアンペアである。 |
| エ | ピン数が9本に増えたので、USB2 . 0のケーブルを挿すことはできない。 |
解答:ア
<解説>
USB3.0とは、USB-IFで標準化が進められたUSB 2.0の次世代規格で、USB 2.0への互換性は保ちながら、最大データ転送速度を5Gbps(USB 2.0の約10倍)にまでアップしている。
スマホ・デジカメで撮った高解像度の画像データや、音声・動画データなど大容量のデータ通信にも適した規格である。
| ア | 〇 | USB2 . 0は半二重通信であるが、USB3 . 0は全二重通信である。 |
| イ | × | Wireless USBは、USB 2.0には対応しているが、USB 3.0には対応していない。 |
| ウ | × | 最大供給電流は、900ミリアンペアである。 |
| エ | × | USB 3.0は、USB2 . 0のケーブルに挿すことができる。 |
問題13
PCをシンクライアント端末として利用する際の特徴として、適切なものはどれか。
| ア | アプリケーションに加えてデータもクライアント端末にインストールされるので、効率的に利用できるが、PCの盗難などによる情報の漏えいリスクがある。 |
| イ | クライアント端末にサーバ機能を導入して持ち運べるようにしたものであり、導入したサーバ機能をいつでも利用することができる。 |
| ウ | クライアント端末の機器を交換する場合、アプリケーションやデータのインストール作業を軽減することができる。 |
| エ | 必要なアプリケーションをクライアント端末にインストールしているので、サーバに接続できない環境でもアプリケーションを利用することができる。 |
解答:ウ
<解説>
シンクライアントとは、ハードディスクを持たない端末で、ネットワーク経由でサーバーに接続して利用する端末。サーバー側でアプリケーションの実行やデータ管理を行うため、端末にデータが残らないという特徴がある。
| ア | × | シンクライアントでは、端末に記憶装置を持たないため、データの流失や紛失といったデータ漏洩事故を防ぐことができる |
| イ | × | シンクライアントはサーバ機能を持たない。 |
| ウ | 〇 | クライアント端末の機器を交換する場合、アプリケーションやデータのインストール作業を軽減することができる。 |
| エ | × | 必要なアプリケーションはサーバからダウンロードするので、サーバに接続できない環境の場合はアプリケーションを利用することができない。 |
問題14
物理サーバのスケールアウトに関する記述はどれか。
| ア | サーバのCPUを高性能なものに交換することによって、サーバ当たりの処理能力を向上させること |
| イ | サーバの台数を増やして負荷分散することによって、サーバ群としての処理能力を向上させること |
| ウ | サーバのディスクを増設して冗長化することによって、サーバ当たりの信頼性を向上させること |
| エ | サーバのメモリを増設することによって、単位時間当たりの処理能力を向上させること |
解答:イ
<解説>
スケールアウトとは、システムを構成するサーバーの台数を増やすことで、システムの処理能力を高めることをいう。
スケールアウトと対照的な方法として「スケールアップ」がある。サーバー台数を増やすスケールアウトに対し、スケールアップはCPUやメモリなどのサーバースペックを増強することでシステムの性能を向上させる。
問題15
フェールソフトの説明として、適切なものはどれか。
| ア | システムの一部に故障や異常が発生したとき、データの消失、装置の損傷及びオペレーターに対する危害が起こらないように安全な状態に保つ。 |
| イ | システムの運用中でも故障部分の修復が可能で、24時間365日の連続運転を可能にする。 |
| ウ | 装置の一部が故障しても、システムの全面的なサービス停止にならないようにする。 |
| エ | 利用者が決められた順序でしか入力できないようにするなどして、単純なミスが起こらないようにする。 |
解答:ウ
<解説>
フェールソフトとは、システム障害時に、機能低下を許しても、被害を最小限に抑えシステムを完全には停止させずに機能を維持した状態で処理を続行する設計である。
| ア | × | システムの一部に故障や異常が発生したとき、データの消失、装置の損傷及びオペレーターに対する危害が起こらないように安全な状態に保つのはフェールセーフである。 フェールセーフとは、異常の発生時にシステムを停止させるか,人間系(オペレータなど)に処理の続行判断を委任し,必ずより安全な状態にシステムを導く方式。 |
| イ | × | システムの運用中でも故障部分の修復が可能で、24時間365日の連続運転を可能にするのは、フォールトトレラントである。 フォールトトレラントとは、信頼性に大きく影響する機器などを複数備えて故障に対処するなどの方法で,システムの信頼性を高める方式。 |
| ウ | 〇 | 装置の一部が故障しても、システムの全面的なサービス停止にならないようにするのはフェールソフトである。 フェールソフトとは、異常の発生時にシステムの機能を縮退させた上で,異常の影響のない機器を活用して,性能が低下しても処理をできる限り継続する方式。 |
| エ | × | 利用者が決められた順序でしか入力できないようにするなどして、単純なミスが起こらないようにするのは、フールプルーフである。 フールプルーフとは、不特定多数の人が操作しても誤操作が起こりにくいように,誤操作自体をできなくしたり,エラーメッセージを表示して処理をやり直させたりする考え方のこと。 |
お問い合わせ